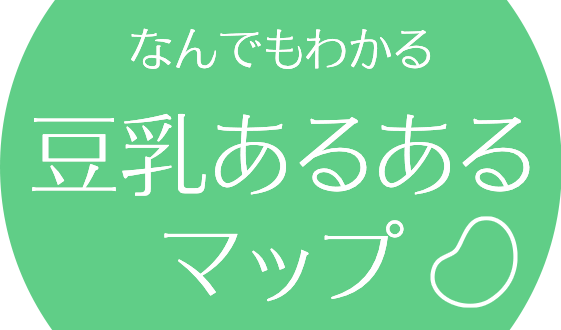疫学研究からみる、妊娠中や幼児期のイソフラボン摂取が与える影響について、愛媛大学の三宅教授が解説
今回は、愛媛大学で疫学研究をされており、イソフラボン摂取に関する研究発表もされている三宅 吉博教授にお話を伺いました。
自己紹介をお願いします。
三宅先生:愛媛大学大学院医学系研究科の教授を務めており、疫学研究をしています。疫学とは、病気にならないためにどうするかという研究です。主に、質問調査票を用いて、調査対象の人たちから様々な情報を得ながら、それらを解析していくという作業を日々行っています。

専門領域などはありますか?
三宅先生:特定の病気や領域にフォーカスはしていません。病気の原因として、タバコがよく挙げられますが、タバコと同じレベルで、食べ物も様々な病気に影響していると考えられますので、質問調査票で情報を得て、広く病気との関連を調べるという方針で研究しています。
それでは、初めに2016年に発表された「大豆製品、イソフラボン摂取が妊娠中うつ症状と予防的な関連」*¹について、研究概要や詳細を教えてください。
三宅先生:この調査は、平成19年に九州のほぼすべての産婦人科の協力を得て、産婦人科を受診されている妊婦さんにお声がけいただき、実施しました。調査の流れとしては、まず、このような調査に興味があって参加しても良いという人を募集し、調査の詳細を説明します。そして、同意が得られた人にアンケートをお送りして、回答後に返送していただくという方法で、最終的に1,757名の妊婦さんに参加していただきました。
その中のアンケートの中に、食事歴法質問調査票という約22ページからなる栄養調査票が含まれており、その栄養素の解析で、様々な食品や栄養素の摂取量を評価することができます。今回の研究では、大豆製品とイソフラボンの摂取量を評価しました。
病気については、明らかな医師の診断だけではなく、アンケートでうつに関する質問(CES-D)に回答いただき、調査をしました。CES-Dとは、Center for Epidemiologic Studies Depression Scaleの略称で、20項目の質問で、うつ症状を評価する質問調査票です。各項目に点数をつけて、16点以上の場合はうつ症状があると決めることができます。今回は、栄養調査票と一緒に回答いただき、それを用いて、栄養素とうつ症状の関連性について解析しました。
調査に参加した1,757名の妊婦さんのうち、最終的にデータが揃っている人が1,745名いました。その内、うつ症状ありの人が19.3%という結果となりました。
栄養素の調査票では、最初に、総大豆摂取量というものを評価しているのですが、今回は豆腐と豆腐製品、納豆、大豆の煮物、単品の味噌、味噌汁、豆乳の合計を総大豆摂取量ということにして、1,745名の摂取量それぞれを評価しました。そして、最も摂取の少ない方から最も多い方を1,745番目までランキングして、摂取量に応じて四等分しています。
つまり、最も摂取していない方から436番目の人、437番目から436人、さらにその次の436人、そして、最も摂取の多い437人というように4つのグループに分けます。そして各グループのうつ症状の割合を比較しました。
1,745名の内、最も摂取の多いグループでは26.2%、次のグループでは19.5%、その次が17.4%、最後が14%というふうに大豆の摂取が多いほどうつ症状が少なくなる結果となりました。さらにこれを統計解析で、大豆摂取量以外の喫煙、お酒などいろいろな要因を考慮に入れた解析をして、最も総大豆摂取量が多い群では、37%うつ症状が少ないという結果が得られたということです。
同じように豆腐だけの摂取量でも同じような結果が出ています。また、豆腐製品でも同じ結果が出ています。さらに納豆、大豆の煮物、味噌汁も同様で、摂取が多いほどうつ症状が少ないという結果になっています。
つまり、大豆製品や豆乳を普段の食事に摂り入れて、イソフラボンの摂取量を増やすことで、うつ症状が軽減、予防されることが期待できるということでしょうか。
三宅先生:はい。今回の研究では、イソフラボン自体の摂取が多くなれば、妊娠中のうつ症状に予防的という結果が得られていますので、豆腐や大豆の煮物に限らず、大豆イソフラボンを含む豆乳も、同様の効果が期待できると考えられます。
ただし、疫学研究というのは、この研究成果だけで結論を出すというものではありません。そのため、今後結論がどうなるかというのは、このような疫学調査を継続して、情報を蓄積していき、最終的にどのようになるかを見定めていく必要があると思います。

また、その後2021年にも世界初の研究成果として、妊娠中の大豆、イソフラボン摂取が幼児の多動問題等に予防的であるという論文*²も発表されていますね。
三宅先生:これは先ほどの調査に参加した1,757名の妊婦さんに参加していただきました。元々この調査の目的は、出産後の母親と子どもを追跡していくというものです。そのため、子どもの出生時にもアンケートに答えていただき、生後4ヵ月、1歳、2歳、3歳、4歳、5歳と追跡調査を行っています。そして現在では、高校2年生に調査が入っています。疫学研究とは、このように息の長い調査をします。
今回の調査では、強さと困難さのアンケート(Strength and Difficulties Questionnaire)という、25個の質問からなる、行動的な問題を評価する国際的な質問調査群を使用しました。これは何ヵ国語にも訳されて世界中で使用されており、行動的問題の中でも情緒問題、行為問題、多動問題、仲間関係問題、向社会的な行動という5つの尺度を評価することができます。うつ症状の質問票と同様に点数化ができるため、何点以上だったら情緒問題が疑われる、というような評価をします。
2021年の研究では、5歳児のデータを使用しました。そのため、親が子どものことについて回答しているので、親の感覚によって子どもの問題を少しきつめに捉える人、優しめに捉える人がいます。さらに、国によって点数の基準はバラバラになっていますが、日本で過去に調べられた基準を使用して、問題が疑われる、あるいは臨床的にそのような問題があるだろうという点数の人を、そのような状態があると考えて評価しています。
妊娠中の大豆製品、イソフラボンの摂取に関しては、2016年と同様のデータを使用しています。解析の結果、情緒問題、行為問題はいずれも関連がありませんでしたが、多動問題に関しては、総大豆摂取量、特に納豆の摂取量が多いほど、5歳児の多動問題に予防的であったという結果が得られました。イソフラボンも同様に、摂取が多いほど、多動問題に予防的という結果が得られています。そして、仲間関係問題に関しては、総大豆摂取量のみ多いほど予防的であるという結果に至りました。
これに関しては、豆乳は飲んでいない方が結構いて、解析対象にはできていないため、豆乳の摂取を全くしていない人が一定数いるというのが、解析が難しいところではあります。
しかし、イソフラボンが多動問題に予防的であるというのは、この研究で出てきた結果です。そのため、イソフラボンが含まれる豆乳を摂取することでの予防的効果の可能性も否定することはできません。

現在の高校2年生を対象とした調査は、そのような内容で進められているのですか?
三宅先生:子どもの調査ももちろんですが、母親が更年期に入ってきますので、その健康問題も調べていけたらと考えています。
また、5歳の時に調査した行動的問題は17歳くらいまで有効なため、高校2年生までは毎年積み上げて質問しています。中学校からは、妊娠中のうつ症状で使用したCES-Dという調査票も使用しています。割合としては、妊婦さんよりは中学生のほうが、若干うつ症状の点数が高いという感じがしています。イソフラボンや大豆に関する調査はまだ評価していませんが、順次行う予定です。
また栄養といってもとても幅広く、脂肪酸、野菜、果物、抗酸化物質、カルシウム、ビタミン、鉄、マグネシウム、食物繊維など大変多岐にわたります。食品の中でもカテゴリーごとに分けられますので、それごとに評価しています。それだけでもかなり時間がかかります。
過去に、海外の研究でイソフラボンを摂取することが良くないという論文が出て、イソフラボンショックとも呼ばれたこともありました。しかしその論文は、食品ではなく、サプリメントで大量に摂取した場合の論文であり、通常の食品によるイソフラボンの摂取については問題ないとされていますが、いかがですか。
三宅先生:そうですね。欧米人からすると、サプリメントからでないと摂取できないような量を日本人は普通に食事で摂れています。そこが大きな違いで、サプリメントと普通の食品を食べるのは違うということを正しく伝えるべきだと思います。
そして、我々研究者は、イソフラボン摂取には予防的な効果があるという成果が出たら、大々的にそのような成果が出ているという情報を、みなさんにお知らせしていくということが、重要になっていくのではないかと思っています。
*¹「世界初の研究成果! 大豆製品、イソフラボン摂取が妊娠中うつ症状と予防的な関連」2016年10月31日
https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2016/10/161031.pdf
*² 「世界初の研究成果! 妊娠中の大豆、イソフラボン摂取が幼児の多動問題等に予防的論文発表」2021年5月3日
https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/05/20210513_med_miyake.pdf