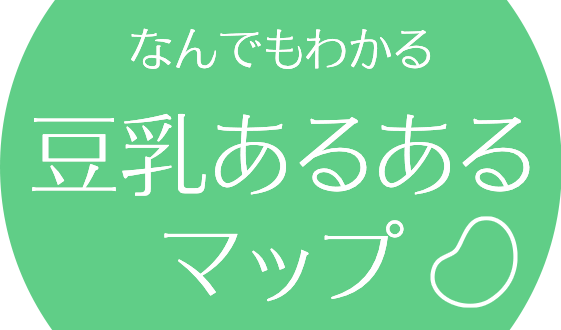青臭みを抑えた豆乳の加工方法とは?~豆乳の可能性を広げる基礎研究について~
今回は、「豆乳の加工工程の見直し」をはじめとする食品加工や製造の最適化に関する研究をされている、静岡県立大学 食品栄養科学部 食品工学研究室の下山田 真教授にお話をお聞きしました。
自己紹介をお願いします。
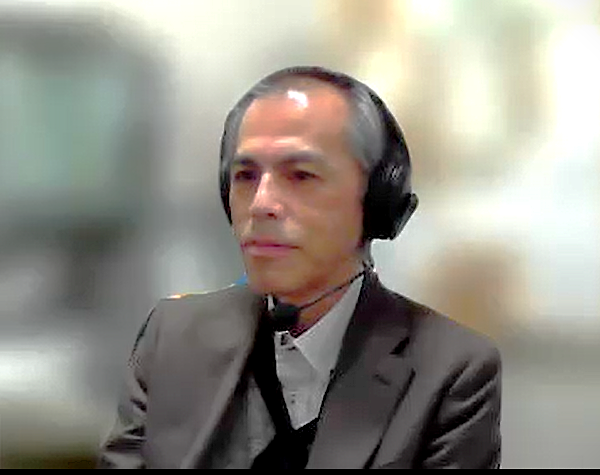
下山田先生:私は、静岡県立大学の食品栄養科学部 食品工学研究室に所属しています。研究分野は「食品をどうやって作るか」ということが、メインターゲットです。食品といっても、世の中には膨大な種類がありますが、その中でも私自身は大豆がきっかけで、長年タンパク質の加工に関する研究をしています。もともと学生時代は農学部で、大豆や大豆タンパク質などの研究をしており、その後、食品加工の研究に進んでいきました。
下山田先生:大豆の栄養というとタンパク質が挙げられますが、様々な加工や調理をした時に、タンパク質がどのように変化して食品になるのかという研究を主に行っています。それに関連して、例えば卵や牛乳などの動物性タンパク質が主体の食品についても研究を進めています。
研究室のHPに掲載されている「豆乳の加工工程の見直し」とは、具体的にどのようなことをされているのですか?
下山田先生:実は、豆乳の加工工程についての歴史は結構古いのです。1960年代頃にアメリカでお湯に丸大豆をそのまま入れて、吸水させずにすりつぶして豆乳を作ると匂いが弱い豆乳が作ることができるという報告があったようです。そこで、例えば何℃で大豆を磨砕するか、何℃で絞るのかなど、条件が様々異なることにより、匂いの出方や、沈殿のでき方に違いが現れるのではないかという仮説を立てました。そして、現在、様々な条件で豆乳を製造すると、どのような違いが現れるのかということを実際に調べています。
それで、良い加工方法が判明したのでしょうか。
下山田先生:何と比べて良いかというと問題はありますが、結果的には、80℃以上の磨砕温度が必要だということが判明しました。そもそも、豆乳特有の青臭みとは、リポキシゲナーゼという酵素が原因です。このリポキシゲナーゼを失活させるために、80℃以上の熱を加えることが必要なため、そのように製造ラインは設計されているのだと思います。
下山田先生:リポキシゲナーゼを失活するという意味では80℃は適した温度でしたが、例えば豆乳の食感や、沈殿の出来具合にも、熱は影響しないのかどうかも調べてみました。その結果、70℃ぐらいで磨砕した場合、ものすごく大量の沈殿が出て、成分の組成もおかしくなりました。しかし、加熱する温度を80℃、90℃と上げていくと、綺麗に分散することが分かりました。リポキシゲナーゼが80℃以上で失活するという理由で、80℃を選んでいたのですが、実は沈殿を作らないという側面でも、80℃以上の温度が必要だったということが判明したのです。

下山田先生:ある一面からだけの結果を見ていると、他の側面の影響や結果を考慮してないことが多いと思います。しかしこの研究では、他の影響についても調べることで、きちんと理に適っていたということが改めて分かり、面白いと思いました。
令和2年に「豆乳はどこまで濃縮できるのか」という研究報告をされていましたが、本件の研究経緯やきっかけについて教えてください。
下山田先生:本研究を始めたきっかけは豆乳ヨーグルトです。豆乳でもヨーグルトが作れるということに驚き、興味を持ちました。そこから、他の食品に加工するのはどうだろうと考えているうちに、豆乳チーズや豆乳クリームが登場してきました。豆乳で色々な食品に加工できるのなら、まだ出来ていない食品はないかと思い調べたところ、コンデンスミルクは作られていないということが分かりました。ではなぜ、豆乳ではコンデンスミルクができないのか調べてみたところ、「豆乳は濃縮できない」という論文にたどり着きました。
下山田先生:それがきっかけで、「濃縮したら何が起こるのだろうか」「なぜ濃縮できないという結論になっているのだろうか」という疑問から研究がスタートし、現在も豆乳の濃縮に関する研究をしています。

豆腐用や飲料用など、加工目的によって基準は異なると思いますが、飲料用の豆乳において高い品質というのはどのような状態のことを指すのでしょうか。
下山田先生:“豆乳をどんなときに飲むか“ということに関わってくるので、これはとても難しい質問です。例えば、暑い時に水のようにごくごく飲む人、お風呂上がりに牛乳の代わりに豆乳を飲むという人、栄養補給のために苦手でも我慢して飲む人、高齢でうまく飲み込めない人など、シーンや対象によって求められる食感や飲み込みやすさなどのニーズが異なるため、一言で”高い品質“といっても、ひとつの基準ではないと思います。そのような様々なニーズに対応して、加工で上手くコントロールすることができないかと思っています。
豆乳の加工食品は、豆乳クリームや豆乳チーズなど様々ですが、加工品によっても、求められる豆乳の品質が変わってくるということでしょうか。
下山田先生:そうですね。加工品によって、成分とか処理の仕方が少しずつ異なります。例えば、ヨーグルトが綺麗に出来るための豆乳、チーズであれば、固まりやすい、チーズになりやすい豆乳など、上手く発酵しやすい豆乳が必要になると思います。
下山田先生:他にも、油揚げは豆腐から作りますが、油揚げにするための豆腐も、普段私たちが食べている豆腐とは少し違います。このようなバリエーションが、豆乳にも必要だと思います。
豆乳の加工工程で、タンパク質やイソフラボンが影響を受けることはありますか?
下山田先生:はい。イソフラボンは大豆に含まれる代表的な栄養素の1つですが、イソフラボンは結構、タンパク質と相互作用しています。加工によって、成分がくっついたり離れたりしています。
例えば、イソフラボンを吸収させやすくするタンパク質があったりするのでしょうか。
下山田先生:そういう成分があったらいいなと思います。実はイソフラボンとは、大豆の中に含まれている時の形と、実際に私たちの体の中で生理機能を発する時の形が違うのです。そのため、体の中で生理機能を発揮する形に、近づけることで、人間が吸収しやすくできないか、ということも研究室のメンバーが研究しています。
こういった基礎研究を重ねることで、大豆や豆乳の加工方法の選択肢が広がったり、豆乳を使用した加工食品のバリエーションが将来広がっていくのですね。
下山田先生:はい、それを目指して日々研究を重ねています。例えば、日本でバターが不足したというニュースが過去にもありました。その要因の1つには、酪農家さんたちが年々減少して供給が難しくなっているということが挙げられます。生クリームを処理してバターにするのは一般的だと思いますが、同じ処理を大豆クリームにすると、トロトロとした液体状の油になってしまいますので、まだ加工の最適条件には至っておらず難しいのが現状です。

下山田先生:ですが、将来的に牛乳で作っている一部の加工商品を豆乳で置き換えて、全く同じラインナップの商品が作れて、それが同じような味だったら、「今日は植物性にしよう」とか「今日は動物性にしよう」というように、消費者のみなさんの選択肢を広げることができると思います。
―――――――――――――――――
下山田先生、ありがとうございました。これからの豆乳の可能性について、とても興味深いお話でした。