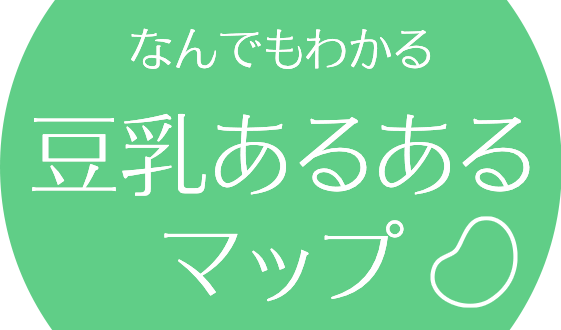和食に豆乳を使うときの活用テクニックをご紹介

皆さんには、お気に入りの豆乳アレンジレシピはありますか。
先日テレビ番組の取材をうけました。その番組が事前に街頭インタビューで一般の人に伺っていた「お気に入りの豆乳アレンジレシピ」に対して、わたくしがコメントするというものでしたが、街行く人から聞いた様々なアイディアに驚かされました。
そのまま飲むだけで楽しむことができる手軽さが豆乳の魅力の1つではありますが、料理に活用してみると楽しみ方がグッと広がります。豆乳は和洋中、その他、料理のジャンルを問わず様々な料理と合いますが、今回は私たちの食卓に馴染む「和食」での活用方法をお伝えしていきます。
「和食」に馴染む♪豆乳の使い方とは?
豆乳は、汁物、麺類、デザートなど様々なメニューに活用することができます。
和食メニューの中で私がすすめる料理は、次の通りです。
汁物:味噌汁、豚汁、けんちん汁など。水を少なめに作り、仕上げに豆乳を加える。
鍋料理:定番の豆乳鍋のほか、キムチ鍋に入れて辛さをマイルドにしたり、すき焼きに入れたりして〆を豆乳うどんすきに。
炊き込みご飯:お好みの具材を入れて味付けをした後、水を少なめに入れて豆乳を加えて炊く。
麺料理:うどん、そば、素麺、ラーメンなどのスープやつゆに豆乳を加える。
料理・お菓子作りに活用する際の豆乳の選び方は?

豆乳を料理やお菓子作りに使う際は、パッケージに記載の次のポイントを確認して選ぶと良いでしょう。
1、名称と原材料をチェック
豆乳には主に、豆乳(無調整豆乳)、調製豆乳、豆乳飲料の3種類があります。料理に使うなら、基本的には原材料が大豆だけの無調製豆乳がおすすめですが、大豆独特の香りが苦手な場合には調製豆乳を好みで使い分けても良いでしょう。調製豆乳は豆乳(無調製豆乳)に糖類や食塩などの調味料を加えた飲料ですので、使用した場合の風味の仕上がりが異なることに注意が必要です。
2、大豆固形分(濃度)をチェック
無調整豆乳の場合は8%以上、調製豆乳の場合は6%以上と日本農林(JAS)規格で決まっていますが、豆乳の風味を楽しみたい場合はなるべく濃い豆乳を選ぶと良いでしょう。
豆乳を料理に使う際の注意点
無調整豆乳を加熱しすぎると、表面に膜(湯葉)ができたり、成分が凝固してもろもろになり、分離してしまったりすることがあります。豆乳は後から入れて沸騰させないようにすると、仕上がりが良くなります。加熱による分離を防ぐために、豆乳鍋やスープにはあえて調製豆乳をという使い方もありますが、その場合は味付けの調整が必要です。
湯葉や豆腐を手作りする場合は、調製豆乳では代用ができず、無調整豆乳でないと上手くできません。豆腐を作る場合はにがりを加えますが、無調整豆乳にお酢やレモンなど、酸が強い食品を加えても、豆乳のたんぱく質が酸凝固して固まる性質があります。その性質を活かした料理を考えるのも楽しいですよ。
和食ごはんを豆乳でアレンジして楽しもう!

今回は、和食をはじめとした料理に豆乳を活用するコツをおつたえしました。皆さんも、毎日の食卓の中で、オリジナルの豆乳アレンジレシピを作ってみてはいかがでしょうか。先日の街頭インタビューでは、残ったカレーに豆乳を加えて楽しむなど、斬新なアイディアがたくさんありました。意外なメニューと相性が良いことが分かったりするなど新たな発見があると、食の楽しみがグッと広がります。
【参考文献】(全て2024年11月25日参照)
農林水産省, 日本農林規格 豆乳類, 2024年3月29日改正
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_standard/attach/pdf/index-321.pdf
【プロフィール】藤橋ひとみ
株式会社フードアンドヘルスラボ 代表取締役、管理栄養士
東京大学大学院医学系研究科修了(医学博士)。すべての人が毎日の食事で 心と体のトラブルを予防・改善できる社会づくりに貢献すべく、レシピ開発、コラム執筆、メディア出演など幅広く活動中。豆乳マイスター“プロ”のほか大豆製品に関する資格を多数取得し、管理栄養士の知識を活かしながら、その魅力を発信している。
【ホームページ】https://is-food-health-labo.com/