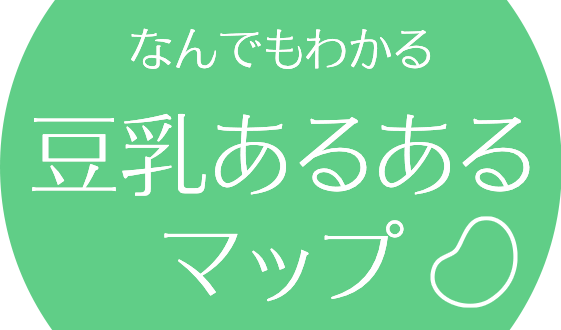より美味しい豆乳をつくる大豆とは?~大豆育種の専門家に聞く~
今回は、農研機構(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)西日本農業研究センターで大豆の育種に携わっている高田 吉丈(たかだよしたけ)さんに、大豆の育種や豆乳に適した大豆のお話についてお伺いしました。
自己紹介をお願いします。
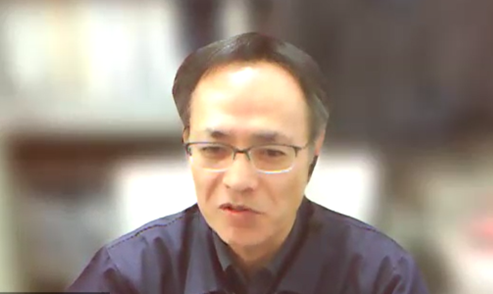
高田さん:農研機構西日本農業研究センターで大豆育種を担当している高田です。農研機構では、大豆の品種育成と関連する研究に取り組んでいます。私は、西日本農業研究センターに所属していますが、農研機構では、東北農業研究センター(秋田県)、作物研究部門(茨城県)、西日本農業研究センター(香川県)、九州沖縄農業研究センター(熊本県)の4ヵ所で大豆新品種の開発を行っています。それぞれの地域に大豆育種の担当者が配置されていて、その地域にあった大豆の新しい品種を作ることを目標に、日々取り組んでいます。
農研機構では、大豆以外の他の農作物も担当されているのでしょうか?
高田さん: そうです。品種育成に限らず、栽培技術の開発や病気に関係する研究をしているところもあります。また、今後重要となるような基礎的な知見を得るための試験を行っているところもあります。基礎から現場まで幅広く農業に関する研究に取り組んでいるのが、農研機構という組織です。
全国各地で大豆の育種を行っているのはなぜでしょうか?
高田さん:大豆は、非常に地域性が高い作物で、作る土地によって合う合わないが品種ごとにあります。例えば、日本で今一番作られている「フクユタカ」という品種がありますが、これは基本的に、西日本地域、東海から九州にかけて栽培することができる大豆です。「フクユタカ」を東北で栽培しようとしても、大豆の特性上、上手く栽培することができません。
一方、日本で3番目に作られている「里のほほえみ」という品種は、東北から北陸、そして北関東で作られていますが、九州、中国地域など西日本では栽培することが難しいのです。このように、それぞれの地域に合う大豆を作るということを目標に、各地で品種育成に取り組んでいます。

地域による影響が大きいのは、どのような点なのでしょうか?
高田さん:一番は日の長さですね。大豆は「短日植物」と言い、日が短くなったことを感じて花をつけ、実をつける作物です。日本は南北に長いので、日中の日の長さの時間は地域によって異なり、それに応じて栽培できるどうかが変わってくるのです。
どのようなことを目標に、大豆の品種育成を進めているのでしょうか?
高田さん:一番重要なのは収量性です。その地域で、たくさん収穫することができる大豆ということを目標に、品種育成を進めています。それから地域によって、さまざまな病害や害虫が発生するので、地域に応じた病虫害抵抗性をつけることも必要です。そして、大豆はさまざまな加工品の原料になるので、豆乳、豆腐、味噌、煮豆などそれぞれの加工品に適しているかどうか、用途別に相応しい品種を作ることを目指しています。
豆乳に適した、青臭みやえぐみを抑えた大豆の育種の育成はどのように進められたのでしょうか?
高田さん:まず大豆の品種育成は、交配育種によって進めていきます。優秀な親を選んで、それを人工交配し、そこから出てくる子どもたち(後代)の中から、育種目的に適した大豆を選んでいくという作業を続けています。

高田さん:豆乳向けの大豆の育種については、農研機構では基礎的な研究を行っているところがあり、まずはそこで、青臭みの元になる成分や、あるいはそれを作り出す遺伝子などの研究を行いました。このような基礎的な研究を進めることで、まずはどのような遺伝子が、青臭み(リポキシゲナーゼという酵素)を出すのかということを突き止めていきました。そしてその基礎研究の結果を用いて、今度は実際の品種に導入するため、人工交配によって青臭みを抑えた品種改良を実現してきました。
高田さん:さらに、豆乳のえぐみのもとはサポニンですが、サポニンにも色々な種類があります。その中でも「グループAサポニン」という成分が、えぐみの元になるということが基礎的な研究で明らかになりました。そして遺伝的な特徴も研究され、サポニンも比較的簡単に品種改良ができるということが分かったので、それも同時に取り込んだことで、青臭みやえぐみを抑えた品種が生まれました。
品種改良はどのくらいかかるものなのでしょうか?
高田さん:通常は、およそ10年以上かかります。交配から始めて、実際に品種登録出願といって農林水産省に登録するのですが、品種としてそこに至るまでは、早くても10年ちょっとはかかっています。
豆乳は青臭みやえぐみを抑えた大豆が適していますが、他の加工品に適した大豆はありますか?
高田さん:それぞれの加工用途によって求められる特性は違います。例えば、豆腐は固まりやすさが重要です。そのため、たんぱく質含量が高いことが必要です。それから、最近ではより美味しい豆腐の要素として、少し甘みがある大豆の需要もあります。
高田さん:味噌は、旨味が重要になってきます。旨味のもとは、やはりたんぱく質なので、豆腐と同様にたんぱく質が高い方が良いとされています。しかし、たんぱく質含有量が高すぎると、今度は旨味が出てこないこともあるので、なかなか難しいところではあります。また、味噌は、加工上、大豆の保水性(水の含みやすさ)も考慮する必要があります。

大豆の育種の中で一番大変なところや難しい点はどこですか?
高田さん:全て大変ではありますが、やはり1年に1回しか作れないということです。年に何回も作ることができない作物なので、そういう意味では1年ごとの勝負になり、さまざまな種類の材料をたくさん扱うことになります。
高田さん:毎年たくさんの組合せの交配をして、毎年一世代ずつ世代が進むことになります。それらを世代ごとに管理し、その中から当初の育種目標に沿って適した大豆を選んでいくという作業を毎年繰り返しています。ある程度世代が進んだら、今度はどれぐらい多く収穫できるのかということを検証します。実際に農家さんに作ってもらった時に、どれぐらいの収穫量があるか、コンバインで収穫するのに適しているのかどうかというテストも全て行った上で、品種を登録します。このように地道に続けてやらなくてはいけないというところが大変です。
やはり実際に育ててみないとわからないことはあるのでしょうか?
高田さん:それはもうたくさんあります。親同士の組み合わせによって、さまざまな形質がバラバラに出てくるので、思ってもみない特性を持った大豆ができることもあります。そのような中から、必要な特徴を持った大豆を選んでいくことが育種作業です。
最近ではどのような大豆の育種が進められているのでしょうか?今後の方針も教えてください。
高田さん:コロナ禍以降、“食料安全保障“が非常にクローズアップされています。食料安全保障は、国内の農業生産の増大を図ることを基本としているため、大豆も例外ではなく、国内生産量をどのようにして上げるかという話になりました。大豆の国内生産量を増やすためには、栽培する土地を増やすことも必要ですが、我々としては、同様の栽培面積で大豆そのものの収穫量を上げることが重要だと考えています。
高田さん:アメリカの大豆品種が持つ、収穫量が非常に高いという特性を国産品種に取り入れるという育種を10年以上前から始めていて、一昨年から昨年にかけて「そらシリーズ」という品種ができました。これは、東北から九州まで、それぞれの地域で「そら〇〇〇」という名前の品種を作っています。国内の大豆生産量を上げることを目標に、大豆の収量のポテンシャルを向上させるために品種育成をしてきた結果、ようやく日の目を見たというのが現状です。
高田さん:現状は、まだできたばかりの品種なので、今後は収量性を維持しながら、国産大豆に必要な品質を保つ高品質化を進めていくことが重要です。おいしい豆乳の原料やおいしい豆腐用の原料のような大豆の特性を今度どんどん取り込んでいき、収穫量が多く、かつ国産の大豆で、各メーカーさんに使ってもらえるような大豆を作るということが、今後の育種の方向性になると思います。
――――――――――――――――――
ありがとうございました。大豆の育種について勉強になるお話でした。