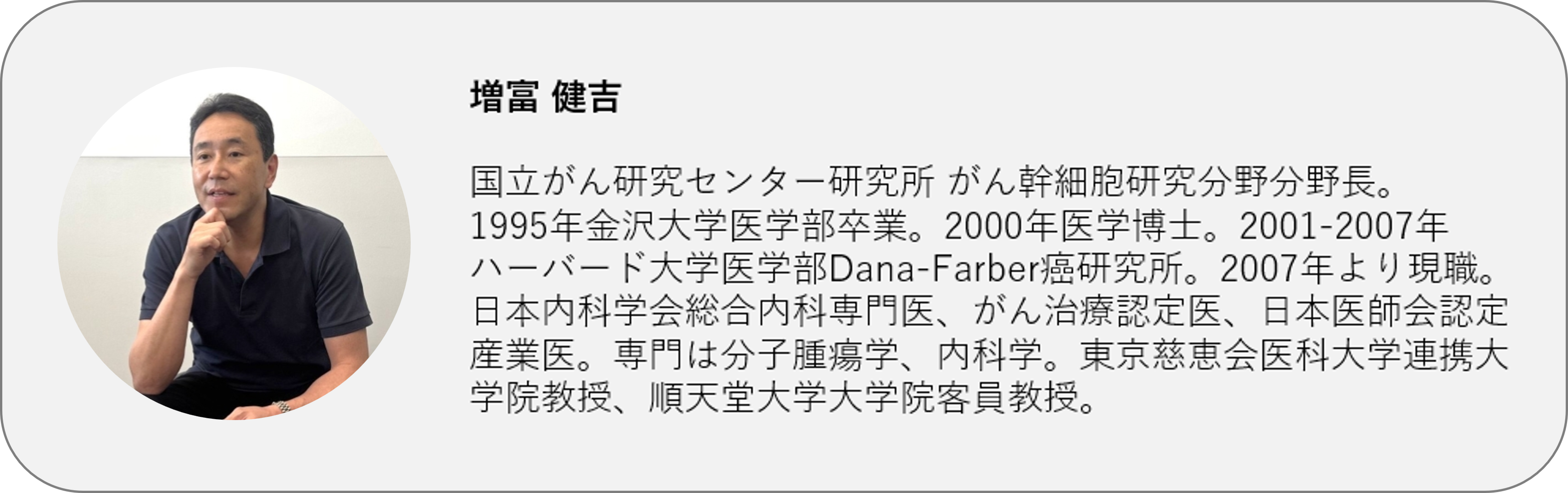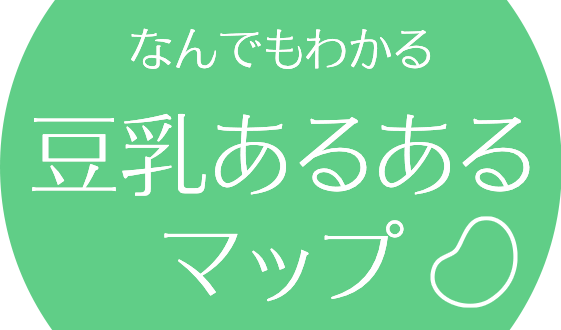【寄稿】 第二回「タンパク質、蛋白質、たんぱく質、プロテイン、protein」
本記事は、国立がん研究センター研究所 がん幹細胞研究分野 分野長 増富 健吉先生より寄稿いただきました。
第1回目では、全ての生物の生命現象の根幹である「タンパク質合成」の材料は3大栄養素のなかの一つであるタンパク質であること、人間はタンパク質を食べることで補っていることを、そして、豆乳はタンパク質の摂取には優れた食品であることをお話ししました。今回は、そのタンパク質、果たしてどれくらいの量が必要なのか等に関してもう少し具体的にお話ししようと思います。

その前に少し余談をしようと思います。皆さんは、「がん」と「癌」の違いをご存じでしょうか?我々の専門の領域の人間にはこの二つの記載の仕方で少し意味が違ってきます。細かい話になりますが「がん」と書けば「広く悪性腫瘍をさす」のですが、「癌」とかけば「組織学的に上皮という組織から発生する悪性腫瘍のみをさし、一般に使用する意味」になります。例を挙げると、「白血病は血液のがん」と書けば正しいのですが「白血病は血液の癌」と書けば専門家的には間違いです。「がん」と書くのと「癌」では意味が異なってきます。
では、タンパク質、蛋白質、たんぱく質、プロテイン、proteinの違いはご存じでしょうか?正解は全て同じ意味ですが、カタカナ表記、漢字表記、ひらがな表記、英語のカタカナ表記、英語表記の違いだけで、全て同じ物を示しています。しかしながら、世間ではどうやら、「プロテイン、protein」といえば筋トレ後に飲む「マッチョの素」の意味で使われている方も多いようですが、本来的にはどの言葉も同じものを指しています。
さて、このタンパク質ですが、1日にどれくらいの量が必要なのでしょうか?大まかな感じでの説明になりますが、体重が50kgの人だとおおよそ最低でも1日50g、60kgの人なら最低でも1日60gという感じでご自身の体重の「kg」を「g」に置き換えた量が、1日の必要な摂取タンパク質量となります。調製豆乳の100mlあたりのタンパク質量が約4gですので、60kgの人が豆乳だけで補おうとすると、豆乳の小さなパックで7から8本分を飲むことになりますので少しハードルが高いですね。同じ量を、動物性たんぱくしつの優等生のささみ、胸肉、牛肉赤身、赤身マグロなどに置き換えると大凡250g程度になります。この量は、通常の運動強度の人の必要摂取量で、例えば、筋トレをしてマッチョになりたい或いはダイエットをしてプロポーションを整えたい、などの希望があればタンパク質必要量はおおよそ1.2倍から1.5倍になります。いかがでしょうか。人が1日に摂取すべきタンパク質量って意外と多いということをまず知っていただければと思います。豆乳だけでとか、ささみだけでというような極端な偏食志向を勧めているのではなく、今の食生活ではタンパク質の摂取量がやや不足気味になっているという意識を持っていただき、ぜひ日々のタンパク質摂取量を増やしていただきたいと思います。

さらに、筋トレマッチョとダイエットについて少し私の持論を書かせていただきます。筋肉をつけることと、ダイエットをすることはいずれも、「高タンパク低カロリーの食事を実践すること」と「運動すること」だと思っています。1回目に3大栄養素の話をしましたが、炭水化物1gは4kcal、タンパク質1gも4kcal、脂質1gは9kcalです。この3つの栄養素を組み合わせて食べて、タンパク質をできるだけ多く摂り、摂取カロリーを抑える食事をするにはどうすればいいか考えてみてください。どうでしょうか?タンパク質をたくさんとって、脂肪を抑えることになりますよね。自ずと炭水化物の摂取量も減らさざるを得ません。筋肉はタンパク質でできていますので、タンパク質の摂取量の多い状況で運動をすれば筋肉はついてきますし、脂肪は燃えて減っていきます。すなわち、このような食事を心がけること自体が、筋トレでありダイエットであるともいえます。高タンパク低カロリーの食事と適度な運動を心がけること自体が筋トレでありダイエットなのです。筋トレ後の「プロテイン、protein」に特にこだわらなくても、いつもの食事に「タンパク質」を加えることで筋トレとダイエットが実践できるということを理解いただけましたでしょうか?

最後に少し、豆乳に多く含まれているイソフラボンという成分について書きます。
天然うなぎの生態はまだまだ未解明の部分が多く、産卵場所や孵化、性の分化に関しては謎の部分が多いそうです。一方、養殖うなぎの多くは「オス」に分化する(してしまう)ことはあまり知られていない事実のようですが、オスのうなぎよりメスのうなぎの方が、大きくて肉厚のため商品としてはメスのうなぎの方が価値が高いそうです。しかし、先にも書きましたが、通常の養殖うなぎはなぜかオスに分化してしまうようです。このうなぎにイソフラボンを含む餌を与えて養殖すると高率にメスうなぎになるとのことです。イソフラボンは女性ホルモンの一つであるエストロゲンに化学構造が似ていますが、もしかしたら、うなぎの性分化への影響もイソフラボンの効果が出ているのかもしれません。そういう意味では、豆乳はタンパク質摂取に好都合な食品である以上に「他にも期待される効果」があるのかもしれません。