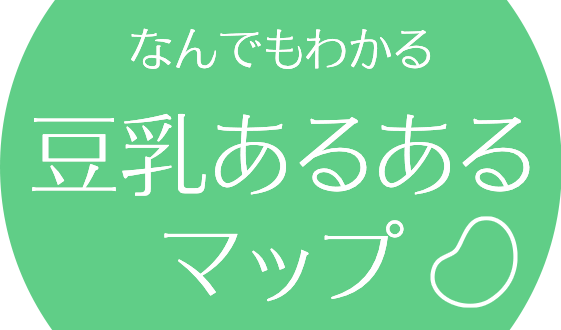豆乳を活用して塩分の摂りすぎを防ごう!
国民病!?高血圧にご用心

和食は脂肪が少なくヘルシーだと言われますが、一方で、塩分が高くなりがちになります。塩分を摂り過ぎると高血圧のリスクも上昇します。日本では成人の3人に1人、高齢者の3人に2人が高血圧と診断されています。高血圧は脳卒中や心臓病など重大な疾患につながりやすいため、高血圧の予防と治療は、今や国民的な課題となっています。高血圧の予防には、「減塩」「体重管理」が効果的ですが、なかでも、毎日の食塩摂取量を制限することが重要です。
食塩は血圧と密接な関係があります。食塩を摂りすぎると、血液中のナトリウムの濃度が高くなり、ナトリウム濃度が高くなると中枢神経に働いてのどが渇きます。のどが渇いて水分を摂ると血管に流れる血液量が増え、血圧が高くなります。つまり、食塩を摂りすぎると体内のナトリウムと水分の量を調整するために血液量が増え、高血圧になってしまうのです。
高血圧状態が続くと血管はいつも張りつめた状態におかれるため、動脈硬化になりやすく、最終的には脳梗塞、心筋梗塞などになる恐れがあります。また、高血圧状態が続くと、心臓に無理な負担をかけることになり、心不全になることもあります。また、同じ血圧でも塩を多く摂っている人の方が脳卒中になりやすいというデータもあります。
日本の高血圧治療ガイドラインでは、高血圧の人に対して食塩の摂取量を一日6g未満にするよう勧めています。しかし高血圧の人に限らず、ほとんどの日本人は必要量をはるかに超える食塩を摂取しています。減塩に対する正しい認識を広め、日本人の生活習慣を改善していく必要があるでしょう。
豆乳で減塩&高血圧予防

塩分の少ない食事といえば、味気ないものというイメージが一般的です。塩分の代わりに豆乳をプラスすれば、アミノ酸のうま味で塩気が少なくてもしっかり味があっておいしい料理を作ることができます。
豆乳には、高血圧の予防に有効な栄養素が豊富に含まれています。豆乳の健康効果は様々なものがありますが、特に注目すべきは、豆乳が血圧に与える影響です。実は豆乳を摂取することで、高血圧のリスクを軽減することができるのです。
豆乳には、ビタミンEやカリウム、イソフラボンなどの成分が含まれています。まず、ビタミンEは抗酸化作用があり、血管を健康に保つ効果があります。カリウムは、ナトリウムの排出を促進してくれるため、塩分を摂りすぎた場合でも余計なナトリウムを体外に排出してくれる働きがあります。その結果、体内の水分バランスが調整されて血液量が減少し、血圧が下がる効果が期待できます。さらに、イソフラボンは血管を広げ、血流をスムーズにすることで血圧を低下しやすくします。そして、これらの成分が相互に作用することで、高血圧の予防に効果を発揮してくれるのです。
まとめ
豆乳を効果的に摂取するためには、飲むタイミングが重要です。朝食時に豆乳を取り入れると、イソフラボンが効率的に体内に吸収されやすくなりますし、寝る前に豆乳を飲むと、リラックス効果があり、質の良い睡眠を促します。
高血圧対策には、ナトリウムの摂取を制限することが重要ですが、同時にカリウムやマグネシウムを含む食品を積極的に取ることも大切です。血圧に影響を与える食品はいろいろありますが、バナナやほうれん草、ナッツ類はカリウムが豊富であり、血圧の調整に役立ちます。豆乳だけではなく、このような食品をバランス良く摂取したり、組み合わせたりすることが、健康な血圧を保つための基本です。一方で、カリウムが摂りすぎた塩分をすべて排出してくれるわけではないので、やはり減塩を心がけることも大切です。

豆乳の選び方のポイントですが、自分の健康目標に合わせて成分表示をしっかり確認しましょう。調整豆乳には少量ながら食塩が加えられているため、減塩目的の方は無調整豆乳がおススメです。豆乳を上手に活用し、健康的な生活を実現しましょう。